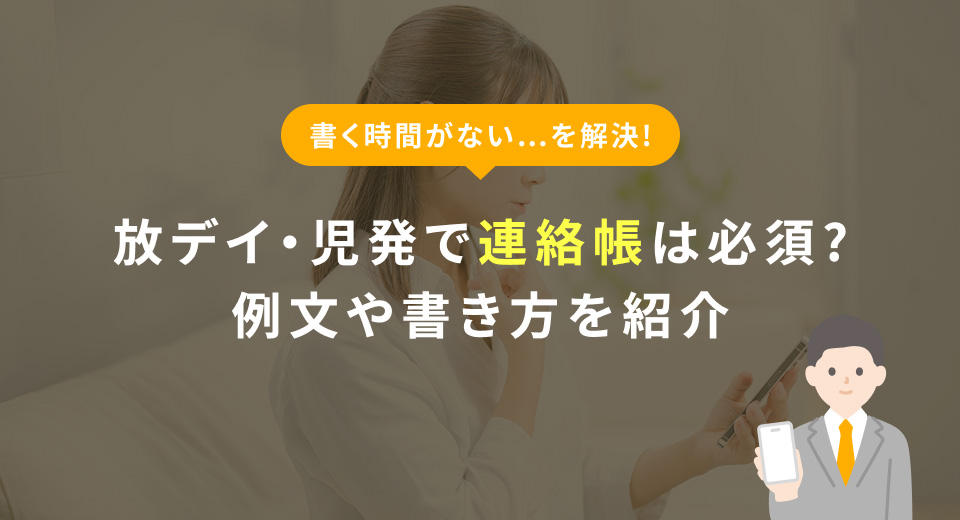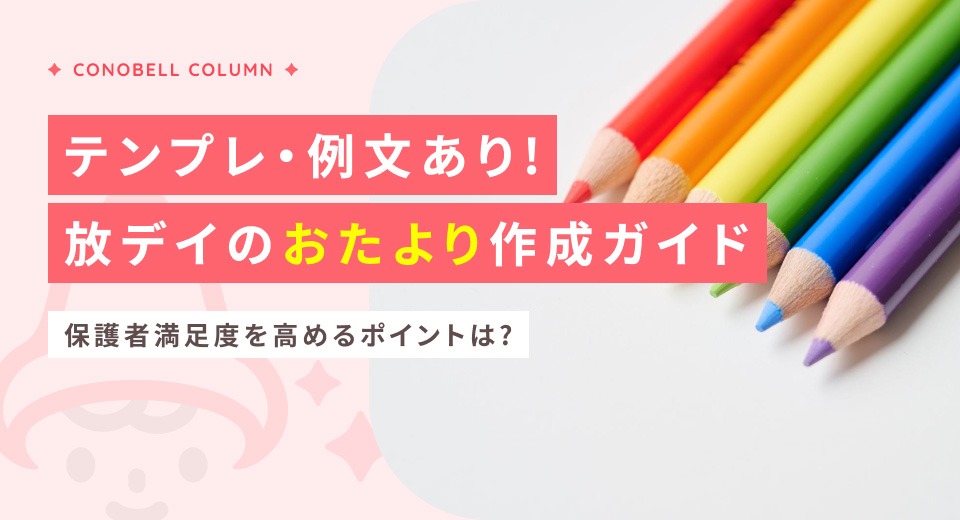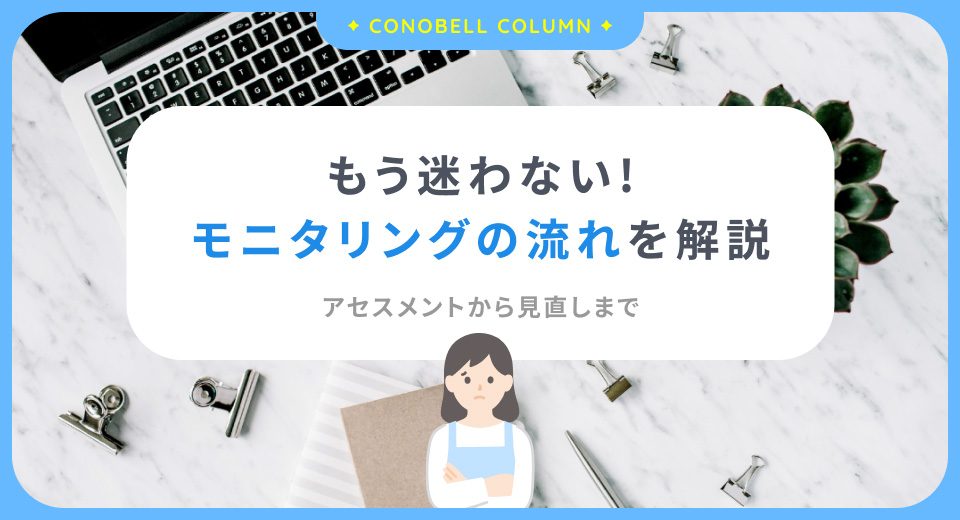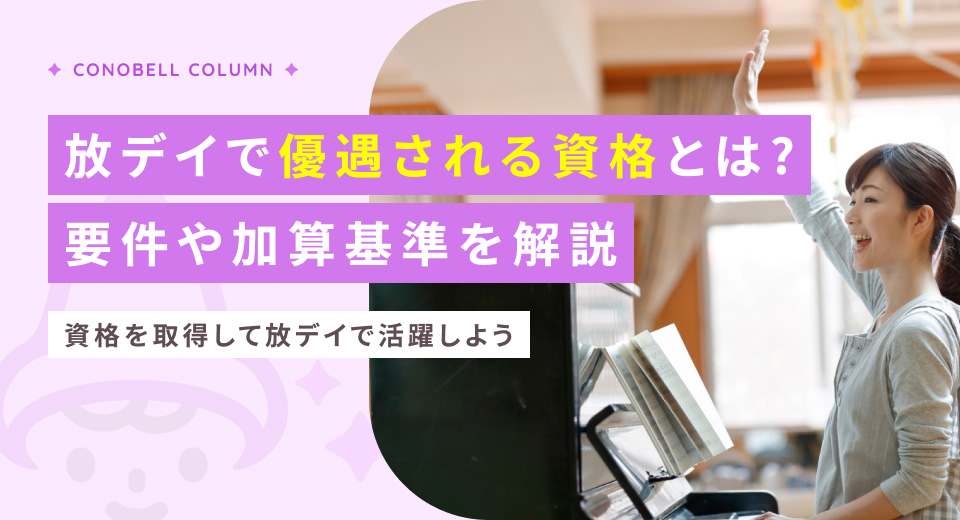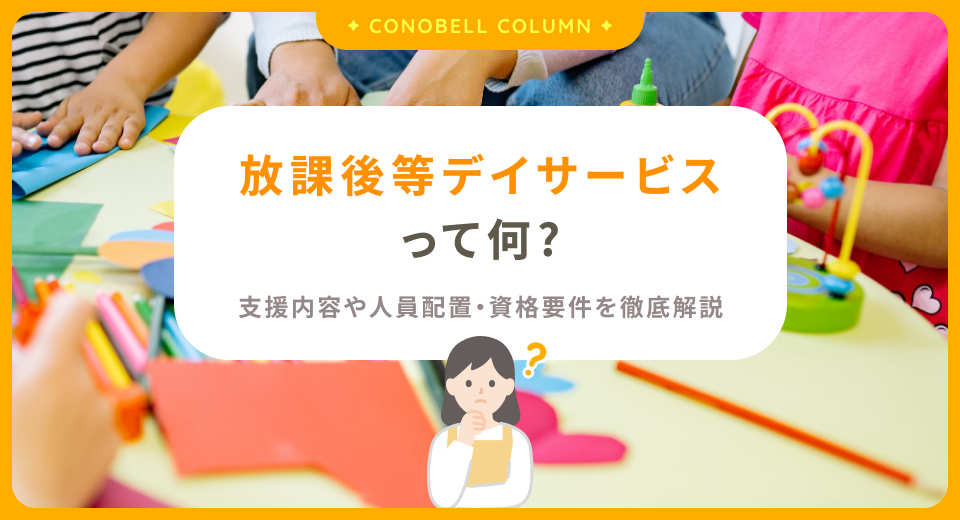児童発達支援事業所とは?放課後等デイサービスとの違いや支援内容を徹底解説!
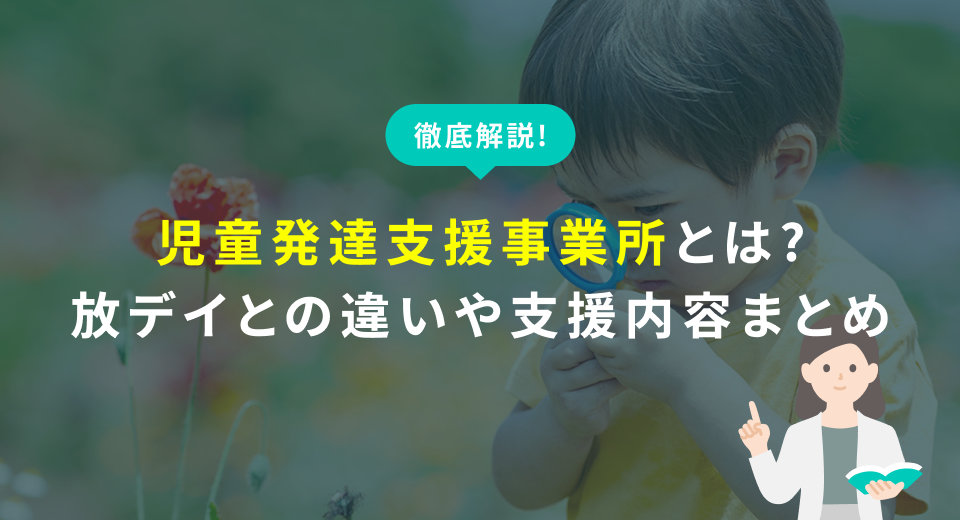
アクセスランキング
児童発達支援事業所は、障がいのある未就学児の発達をサポートする重要な施設です。
この施設では、子どもたち一人ひとりの成長に応じた支援を行い、自立や集団生活への適応を目指します。
また、保護者の相談支援や地域との連携も行うため、子どもと家庭を総合的に支える仕組みが整っています。
この記事では、児童発達支援事業所の概要や放課後等デイサービスとの違い、さらに必要な資格や人員配置、支援内容について詳しく解説します。
目次
児童発達支援事業所とは?

ここからは、児童発達支援事業所がどのような施設なのか、対象となる子どもやその背景について詳しくご紹介します。
児童発達支援事業所とは?障がいのある子どもを支える施設
児童発達支援事業所は、主に障がいを持つ未就学児を対象とした通所施設です。
子どもたちが日常生活で必要なスキルを習得したり、集団生活に適応できるように支援を行います。
例えば、トイレや歯磨きといった基本的な生活動作の指導や、遊びを通じて社会性を育む活動が挙げられます。
また、施設では一時的な預かりを行うことで、保護者に息抜きの時間を提供する「レスパイトケア」の役割も果たしているのです。
対象となる子どもは?診断名や障害者手帳がなくても利用可能
児童発達支援事業所を利用できるのは、就学前の障がい児です。
通所の際、必ずしも医学的な診断名や障害者手帳が必要ではありません。
自治体が発行する「障害児通所受給者証」を取得することで、利用が可能となります。
この仕組みにより、支援が必要な子どもが早期に療育を受けやすくなっています。
児童発達支援事業所と放課後等デイサービスとの違いとは?
ここからは、よく似た施設である「放課後等デイサービス」との違いについて詳しくご紹介します。
対象年齢と利用時間の違い
児童発達支援事業所は、0〜6歳の未就学児を対象に、平日の日中(10時〜13時など)を中心としたサービスを提供する施設です。
主に保育園や幼稚園に通う子どもたちが利用し、日常生活スキルの習得や社会性を育む支援を行います。
一方、放課後等デイサービスは6〜18歳の就学児が対象です。
学校が終わった後の14時以降から夕方にかけて利用でき、学校生活や学習支援、さらに集団活動を通じた社会性の向上を目的としています。
このように、対象年齢や利用時間の違いが、両施設の大きな特徴です。
それぞれの施設が子どもの成長段階に寄り添い、適切な支援を行っています。
支援内容の違い
児童発達支援事業所では、未就学児が日常生活に必要なスキルを身につけるための支援が中心です。
トイレや着替え、歯磨きといった基本的な生活動作の練習や、遊びを通じて集団生活に適応する力を養います。
また、保護者支援やレスパイトケアの役割も担い、家庭全体を支える仕組みが整っています。
一方、放課後等デイサービスでは、学習支援や運動、レクリエーションを通じて、就学児の学業や社会性をサポート。
特に学校生活を円滑に送れるように、個別の課題に対応した支援が重視されます。
このように、支援内容はそれぞれの年齢や発達段階に合わせたものとなっているのです。
児童福祉法改正がもたらした専門性の向上
2012年の児童福祉法改正により、未就学児と就学児が同じ施設で支援を受ける「児童デイサービス」から、現在の「児童発達支援事業所」と「放課後等デイサービス」へと分けられました。
この改正の目的は、年齢や発達段階に応じた支援を提供し、より専門的で効果的な療育を行うことです。
未就学児には、生活スキルや集団活動への適応を重視した支援が行われるようになり、就学児には学習や社会性を育む支援が適切に提供されるようになりました。
この分離によって、子ども一人ひとりのニーズに応じたきめ細かいサポートが可能となり、支援の質が大きく向上したのです。
▼放課後等デイサービスについてはこちらの記事をチェック!
放課後等デイサービスとは?支援内容や人員配置・資格要件を徹底解説
児童発達支援事業所の特徴と支援内容

ここからは、児童発達支援事業所で提供される具体的な支援内容についてご紹介します。
個別療育とは?子どもの課題にじっくり向き合う支援
児童発達支援事業所では、「個別療育」によって子ども一人ひとりの発達や特性に合わせた支援を行います。
この支援方法ではマンツーマンで子どもの課題に直接アプローチし、生活スキルや運動機能、言語能力などを伸ばしていきます。
例えば、「トイレトレーニング」や「着替えの練習」など、日常生活に必要なスキルを段階的に指導していくのです。
これにより、子どもが安心して取り組みやすい環境を整えつつ、目標達成を目指します。
集団療育とは?社会性や協調性を育む活動
「集団療育」では、他の子どもたちと一緒に活動を行い、社会性や協調性を育む支援を行います。
例えば、グループでの遊びやレクリエーションを通して、ルールを守ることや順番を待つことなどを学びます。
また、他の子どもと関わる中で、コミュニケーションのスキルや自己表現の方法を自然と身につけることができるのです。
これらの活動は、将来の集団生活への適応に向けた大切なステップとなります。
家族や地域と連携した支援の大切さ
児童発達支援事業所では、子どもだけでなく保護者や地域への支援も重視しています。
保護者には、子どもの発達特性や家庭での接し方について相談対応を行い、必要に応じて具体的なアドバイスを提供。
また、保護者同士の交流の場を設け、悩みや体験を共有する機会を作ることもあります。
地域の保育園や幼稚園、小学校と連携し、子どもの次のステップへの移行をスムーズにするための支援や情報共有も行われているのです。
これらの取り組みによって、子どもを取り巻く環境全体を整える支援が実現します。
児童発達支援事業所で働くには?人員配置と必要な資格

ここからは、児童発達支援事業所で働くために必要な資格や人員配置についてご紹介します。
どんな職種が必要?児童発達支援事業所の人員配置
児童発達支援事業所では、さまざまな職種が連携して子どもたちを支えます。
それぞれの役割を簡潔にまとめると以下の通りです。
・管理者
施設全体の運営を担当。労務管理や収支管理、見学者対応など運営全般を担います。
・児童発達支援管理責任者
個別支援計画を作成し、サービスの提供を管理する。この職種には、5年以上の実務経験と研修修了が必要です。
・児童指導員/保育士
子どもの日常生活や集団活動をサポート。児童指導員は、専門資格や実務経験が必要ですが、保育士は国家資格が求められます。
・機能訓練担当職員
理学療法士や言語聴覚士、作業療法士など。子どもの運動機能や言語スキルを伸ばす専門的な訓練を行います。
これらの職種が連携し、それぞれの専門性を活かして子どもたち一人ひとりの成長を支えています。
特に児童発達支援管理責任者は、施設の運営を支える中核となる存在です。
どんな仕事をするの?児童発達支援事業所での一日の流れ
児童発達支援事業所での一日は、朝の受け入れからスタートします。
子どもの健康状態を確認し、個別療育や集団療育を行います。
午前中は主に療育活動を行い、その後、昼食をサポート。
午後は遊びやリラックスタイムを通じて子どもの社会性を育む時間を設け、保護者への引き渡しを行います。
また、保護者からの相談対応や、次回の支援計画を立てる業務も重要です。
施設によって活動内容は異なりますが、子ども一人ひとりに合わせた支援が行われることが特徴です。
児童発達支援事業所の利用方法と費用
ここでは、児童発達支援事業所を利用するための手続きや費用についてご紹介します。
利用するための手続き
児童発達支援事業所を利用するには、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。
受給者証を申請する際、自治体の担当者が子どもの発達状況を調査し、必要な支援内容を判断します。
発行までには数週間から数ヶ月かかることもあるため、早めの準備が大切です。
利用料金は世帯収入によって異なる
児童発達支援事業所の利用料は、世帯の収入状況に応じて負担額が異なります。
例えば、住民税非課税世帯であれば利用料は無料ですが、課税世帯の場合は月額4,600円〜3万7,200円の負担となります。
まとめ
児童発達支援事業所は、障がいのある未就学児を対象に、個別のニーズに応じた支援を提供する施設です。
放課後等デイサービスとは対象年齢や利用時間が異なり、それぞれの役割が明確に分かれています。
施設では子どもだけでなく家族や地域全体を支える仕組みが整っており、利用者や働く人にとっても充実した環境が用意されています。
障がい児の成長を支える重要な役割を担う児童発達支援事業所について、ぜひ理解を深めてみてくださいね。